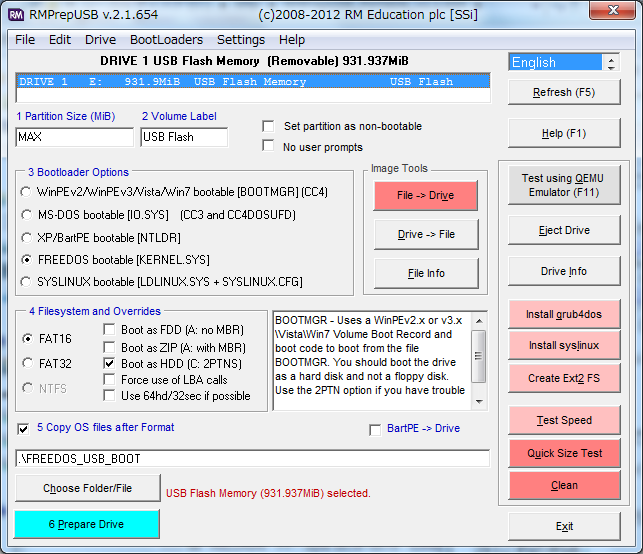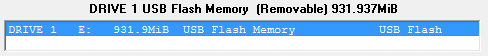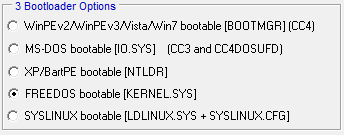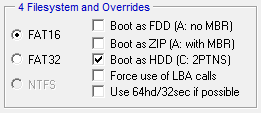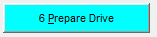USB温度計 TEMPer V1.2向けの温度計測ソフトウェアpcsensorを、自分の使い道にあうように改造しました。
・http://blog.osakana.net/sw/pcsensor/pcsensor-1.0.2.tar.gz
元となったプログラムは以下の2つ。
・Juan Carlos Perezさん製作: http://www.isp-sl.com/pcsensor-1.0.1.tgz
・Momtchil Momtchevさん製作: pcsensor-1.0.0-multi.tgz (Juanさんのpcsensor-0.0.1.tgzを元にしている)からマルチデバイスサポートのやり方
追加した機能
・マルチデバイス時にデバイス名を出力するオプション “-d”
# ./pcsensor -d 2013/01/20 14:42:13 Bus 002 Device 003 Temperature 88.47F 31.38C 2013/01/20 14:42:13 Bus 003 Device 003 Temperature 74.30F 23.50C #
・接続されているTEMPerのリスト表示 “-D”
# ./pcsensor -D 0 is Bus 002 Device 003 1 is Bus 003 Device 003 #
・接続されているTEMPerの個別表示 “-D番号”
# ./pcsensor -D0 2013/01/20 14:43:48 Temperature 88.47F 31.38C # ./pcsensor -D1 2013/01/20 14:44:16 Temperature 74.30F 23.50C #
・摂氏/華氏表示の同時指定を可能にした
# ./pcsensor -c 2013/01/20 14:44:49 Temperature 31.38C 2013/01/20 14:44:49 Temperature 23.50C # ./pcsensor -f 2013/01/20 14:44:53 Temperature 88.47F 2013/01/20 14:44:53 Temperature 74.30F # ./pcsensor -f -c 2013/01/20 14:45:02 Temperature 88.47F 31.38C 2013/01/20 14:45:02 Temperature 74.30F 23.50C #